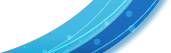|
 |
*就労ビザ
ここでは、就労ビザを、外国人雇用の視点で解説致します。なお、専門知識の無い方に分かりやすくする工夫として敢えて「就労ビザ」という言葉を用いており、専門家にはかえって読みにくいかもしれませんがご諒承頂きたく。
Q:就労ビザとは何でしょうか。
A:就労ビザとは、本来、法令用語ではなく、慣用語句ですが、「就労」が可能になる「ビザ」であるともいえます。
まず、ここでの「就労」とは、本邦において「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」(入管法19条1項1号2号等)をいいます。この「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」の定義は重要で、資格外活動の対象になるほか、短期滞在の在留資格該当性の基準にもなります。
次に、就労ビザの「ビザ」とは、元々は「査証」の意味だったのですが、世間一般に「ビザ」という場合、上陸許可、在留許可、就労許可、の意味合いで用いられる場合が多いといえます。その意味でいえば、「資格外活動許可」も「ビザ」であるという表現もできるでしょう。
こうした意味の「就労ビザ」は法令で類型化されており、「技術」「企業内転勤」「人文知識・国際業務」等の在留資格が定められ、その在留資格毎に、意義・要件・効果が規定されています。
Q:元々外国の子会社から日本の親会社A社に来ていて、既に日本のA社で「技術」の在留資格という就労ビザで就労している外国人につき、日本にある同じA社にて勤務したまま、「企業内転勤」の在留資格に「在留資格変更許可申請」を行って許可される余地があるか、基準省令では「申請に係る転勤の直前に・・・1年以上・・・」とあるので、この場合は、申請前1年は、日本にある同じA社のままともいえ、この場面の就労ビザの要件たる「転勤」といえないのではないか等が問題となります。
A:
A説(否定説。入在、東京入国管理局インフォメーションセンター結論同旨。)
結論:変更申請(就労ビザ)は許可されない。
理由:(1)基準省令には、「申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において1年以上継続して法別表第1の2の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。」と規定されているところ、そのような場合には、同じ事業所にて勤務している状態に変動が無く、少なくとも文理上、「転勤」と解するのは困難である。
(2)企業内転勤(という就労ビザ)はそういうものではありません。海外に勤務していなければなりません。そのような場合には転勤と解釈不可能であり、変更の許可の余地はありません(東京入国管理局インフォメーションセンターの打診結果要旨。)。
B説(肯定説。東京入国管理局就労審査部門結論同旨。)
結論:(他の要件を充たせば)変更申請(就労ビザ)は許可される。
理由:(1)そもそも「基準省令上、転勤の直前に一年以上継続して業務に従事していたことを求めているのは、本邦における労働力を確保しようという目的のためだけに、その企業の業務に関して何ら専門的知識を持たない新規従業員を本邦に転勤させることを防止するためで」あるから(「人流」2003・6・46頁)、「直近一年の業務・・・が本邦における」技術の在留資格での業務「であったとしても、当該」技術の在留資格での業務「が海外現地法人の業務の一環としてのものであるならば、本邦にある本社において」技術「の在留資格をもって行っていた活動も直近一年の業務に従事していた期間とみなすことができます。」と解する(以上、「人流」2003・6・46頁の「研修」を「技術」に置き換えたものです。)。
(2)「照会の事案については、変更申請した場合、(就労ビザを)許可する余地は存する。但し、以下に注意されたい。」「まず、現在のところ、雇用形態と給与の支払い形態を一致させる見解を採用し、たとえば、韓国の法人で雇用契約=韓国で給与支払=企業内転勤(という就労ビザ)の該当性、と解し、日本の法人で雇用契約=日本で給与支払=技術又は人文国際(という就労ビザ)の該当性、という判断基準で形式的に分別している。なお、法務省本省のサイトに、これ(就労ビザ)に関する解釈が表明されていることは承知しているが、現場ではこれで特に問題は無い。したがって、現在の東京入管は、外国で給与が支払われている場合には、技術や人国(という就労ビザ)の該当性があるとは解さず、企業内転勤(という就労ビザ)の該当性で判断する。逆に、日本で給与が支払われている場合には、企業内転勤(という就労ビザ)の該当性があるとは解さず、技術や人国(という就労ビザ)の該当性で判断する。」「然るに、照会の事案については、これまで技術の在留資格(就労ビザ)で在留していた以上、日本で給与が支払われていたはずであるから、これを企業内転勤(という就労ビザ)に変更申請したい場合、給与を韓国で支払う必要がある。また、雇用形態も、韓国の法人で雇用契約を締結している必要がある。」「なお、直近1年間の従事の要件については、そのような場合でも転勤と解釈可能であり、変更の許可の余地は存する。」(東京入国管理局就労審査部門の打診結果要旨。)。
<コメント>
私見は疑義が存するので、かかる見解に与するものではないが、企業としては、B説(又は、それに準じた見解)を採用するべきであると入管に主張し、理由書にその旨の解釈を書いたうえで、申請することになると思われる。私見では、そのようにして解釈を述べた理由書を付けて申請すれば、求めるタイプの就労ビザも許可される余地が無いとはいえないと解される。もっとも、就労ビザの「変更」申請ではなく、いったん帰国して就労ビザの「認定」の申請なら可能である等の解釈が入管サイドから出てくるといった可能性もあると思われる。
<補足>
そもそもなぜ、このような論点を議論しているかといえば、「技術」は「日本で、必ず、給与を支払う必要がある」が、「企業内転勤」ならば、一般には日本で支払うものであるが、海外の子会社等で支払っても構わない(その場合、更新時の年間給与支払いの証明書は海外法人作成名義での発行のもので構わない。外国政府発行の納税証明書等は基本的に要らない。)、という通説的ドグマがあるからである(東京でも横浜でも確認済。)。そのため、企業内転勤に変更したいというニーズが発生する。
さて、東京入国管理局就労審査部門の見解に対し、入在の担当者のほうでは、技術と企業内転勤の区別に関しては、別異の回答を開陳している。曰く、企業内転勤の場合でも、日本の企業との間に雇用契約関係は必須であるという(しかし、内部資料ではそうではない。そのうえ、「人流」2001・08・46もそうではないので、疑問が存する。)。その理由として、たとえ親子会社等であろうともあくまで別の法人であり、本邦の法人との間に雇用契約関係が無いのはおかしい、契約関係があるはずであるという。また、企業内転勤の場合でも、むしろ、日本の会社のほうで、給与を支払うのが原則であると主張される。ただ、入在の立場であっても、企業内転勤の場合、母国の子会社や親会社のほうで、給与を支払うことは妨げない。
東京入国管理局就労審査部門と入在の見解は矛盾する。さらにそのうえ、横浜に照会したところ、疑義が存するので、直接、統括が面談するから、来られたしという(但し、「呼び出し」で多忙にて、数日後。)。
結局、この問題については、通説は存しないか、少なくとも、入国管理局で統一はされていないものと推定されよう。通説が存しない場合、現場では「自由裁量」が強力に適用されるであろう。興行や就学の審査で局等によって、許可率にも、所用の証拠資料にも、審査時間にも、大きく差が出るように、入国管理局という行政には、審査基準など、あってないようなものである。はっきり言って、審査基準などほとんど飾りである。いわば、憲法学の「違憲審査基準論」のようなものである。実際、現場の職員は、審査基準など無いほうがよいと思っているきらいがある。このことをよく意識しておく必要がある。しかし、無いよりはマシなのであろう。それが、「違憲審査基準論のようなものである」という所以である。
そもそも、基準の制度趣旨自体が明確ではない。民法や憲法で言えば、注釈民法等の膨大な蓄積があるが、入管法には学問的蓄積は、民法等と比べれば、無いも同然である。解釈論を展開するうえでは、制度趣旨の理解が必須である。このような場合において、行政書士は果敢に申請を行い、解釈論の発展に寄与しなければならないと解される。
2005Nov15
Q:甲社は、現地法人である100%子会社の乙社に半年間勤務していた社員丙を、技術の在留資格で、日本に招聘し、半年間日本で就労していた。その後、社内の方針により、丙は帰国し、元の子会社である乙社に戻り、さらに半年間が経過した。この場合に、丙を認定で招聘するとして、企業内転勤の「1年」の要件を充足するか。なお、乙社は丙を日本に行かせていた間も、雇用契約を解消したものではなく、乙丙間の雇用関係は継続していたものとする(重畳的雇用関係)。ゆえに、その期間の在職証明書は、重複して発行されることになる。なお、送り出し国では、日本への「出張」中、給与は払っていないが、外国出張手当は支払っている。しかしながらその手当というのは微々たるもので、その国での社会保険料(日本への「出張」中も、当然、社会保険は継続している。)を差し引くとマイナスになってしまう程度のものであった。※なお、親子会社と雖も別法人である。
A:
A説(肯定説。入在、某職員)
結論:充足する。
理由:(1)乙丙間の雇用関係が継続しているならば、乙社の業務の一環であったと評価可能。
(2)同様の場面で研修で肯定例があるので、勿論解釈である。
批判:それを認容するなら、過去1年間、日本に「技術」で在留していた場合に、技術→企転の変更申請を許可するべきはずである。しかし、変更申請については不許可事例があり、矛盾する。
B説(否定説)
結論:充足しない。
理由:乙丙間の雇用関係が継続していたといっても、そもそも技術の在留資格は、本邦の企業との間に雇用契約を締結したゆえに、許可されたものであり、甲社の業務に従事していたと評価できても、乙社の業務の一環であったとの評価はできない。
批判:企業内転勤の在留資格の「1年」の要件を設けた制度趣旨を理解していないのではないか。
2007May09
Q:たとえば、労働者派遣法に基づく、日本の派遣会社A社、A社の中国の現地法人B社、日本の派遣先会社C社があるとします。この場合に、B社からA社に対し、「企業内転勤」の在留資格で転勤し、そのうえ、A社からC社に対し、労働者派遣法に基づき、人材を派遣することが可能でしょうか。
※設例
B社(現地法人)→→→A社(派遣元)→→→C社(派遣先)
[1年以上勤務]
[ABは資本関係有]
A:その設例ですと、C社とは、通例、資本関係がないことから、「企業内転勤」の要件を欠き、許可することは困難。つまり、派遣業で外国人を派遣する場合、その在留資格は、通例、「企業内転勤」ではなく、「技術」や「人文知識・国際業務」等になります。このことは、「企業内転勤」と「技術」や「人文知識・国際業務」の申請書を比較すれば分かりますが、「企業内転勤」の申請書では、労働者派遣法に基づく派遣を予定した項目が無いのです。したがって、もし、外国人を派遣するために、現地法人を設立し、そこに外国人を採用したとしても、企業内転勤の枠では派遣業で派遣することを前提に招聘することができず、意味がないことになります。ちなみに、「技術」や「人文知識・国際業務」で、派遣業の会社が外国人を招聘する場合、現地法人が存在している必要はありません。したがって、派遣業で外国人を派遣したい場合には、現地から外国人を広告等で直接募集し(面接等は短期滞在の在留資格で可能な場合があります。)、派遣先に引き合わせる前に履歴書や職務内容等で、就労系の在留資格を取れるのかを事前に判断し、そして、面接でOKならば、A社が(派遣先の会社や職務内容を必ず特定したうえで)入管に「在留資格認定証明書」を申請し交付のうえ(変更許可が可能な在留資格を既に持っているのならば、端的に変更申請でもよいです。短期からの変更は、就労系は普通はやりません。)、査証発給、上陸許可を経由し、そして、派遣業の会社のA社が直接、採用、雇用のうえ派遣すればいいということになります。現在の一般的な入管での法令解釈においては、「企業内転勤」の場合、B社が雇用し(その状態は日本へ転勤しても変わらない。)、「技術」や「人文知識・国際業務」では、A社が雇用する、という関係だと解されています。また、「企業内転勤」との違いとして、「技術」や「人文知識・国際業務」では、現地法人に1年以上在職している必要はないものの、「技術」や「人文知識・国際業務」の場合は、「企業内転勤」の場合よりも、学歴や職歴等の要件が厳しく求められる点が挙げられます。
※「企業内転勤」・「技術」・「人文知識・国際業務」の主要な差異
「企業内転勤」 「技術」 「人国」
__________________________________________________________________________________________________
*現地法人等に1年以上在職 要 否 否
*学歴や職歴等の要件 本来不要 要 要
(参考文献:人流2001・8・47頁・問4等)
Q:「技術」や「人文知識・国際業務」で招聘するとして、派遣業で外国人を派遣する場合、派遣元としては、在留資格認定証明書を申請する前に、必ず、派遣先会社名や派遣先での職務内容、を特定しておかねばならないのでしょうか。
A:特定しておかねばなりません。そもそも、就労系の在留資格の場合、一般に、「活動の内容」、「期間」、「地位」、「報酬」が審査の対象になりますが、派遣業で他社に派遣する目的で招聘する場合、これらの要件は、派遣元と派遣先の両方で問題になるからです(例、派遣元での地位は派遣社員ですが、派遣先での地位は、ソフトウェアエンジニア等。)。申請書でも派遣先は予め特定して書くようになっています。なお、職務内容と学歴等が一致するかどうか、といった問題は、派遣先での職務内容で審査されます。
Q:派遣業で外国人を派遣することを前提に招聘する場合、そうでない通常の就労の場合(あくまで自社内で就労させるだけで派遣業で派遣しない場合)と、提出資料はどのように違うのでしょうか。
A:審査対象が派遣元と派遣先の両方になるため、まず、会社に係る書類が、派遣元と派遣先の両方が必要です。即ち、会社案内パンフレット、法人登記簿謄本、損益計算書の三点については、派遣元と派遣先の両方に必要です。したがって、派遣元は、認定証明書を申請する前に、派遣先に説明して、これらの資料をもらっておく必要があります。派遣業ではない場合とパラレルですから、たとえば、派遣先が新設会社等の場合で、損益計算書がない場合、派遣先の当該事業に係る事業計画書が必要です。このようにして、就労の「安定性」と「継続性」が、派遣元と派遣先の両方で審査されるのです。
また、派遣元と派遣先の間の会社間の派遣契約に係る契約書のコピーも必要です。さらに、もちろん、派遣元と被雇用者たる外国人の間の雇用契約書ないし採用通知書の類のコピーも必要です(但し、これは、派遣の場合に固有のものではありません。)。しかし、これらについては、派遣期間等、労働者派遣法等の労働関係法令を遵守している必要があります。したがって、派遣業で外国人を派遣する場合、入管と労働基準監督署の双方が関わるといえます。
さらに、新規事業として、派遣業を開業したような場合は、労働者派遣業の許認可に係る証明書のコピーも出すべきでしょう(大手派遣会社や既に申請実績のある会社では通例、要りません。)。
以上を要するに、派遣業の場合、派遣元を甲、派遣先を乙、外国人被雇用者(派遣社員)を丙、とした場合、甲・乙・丙、のいずれか一人でも法的に不備がある場合、許可されないことになり、ある意味、ハードルの高い申請だとも言えます。
|
|
 |